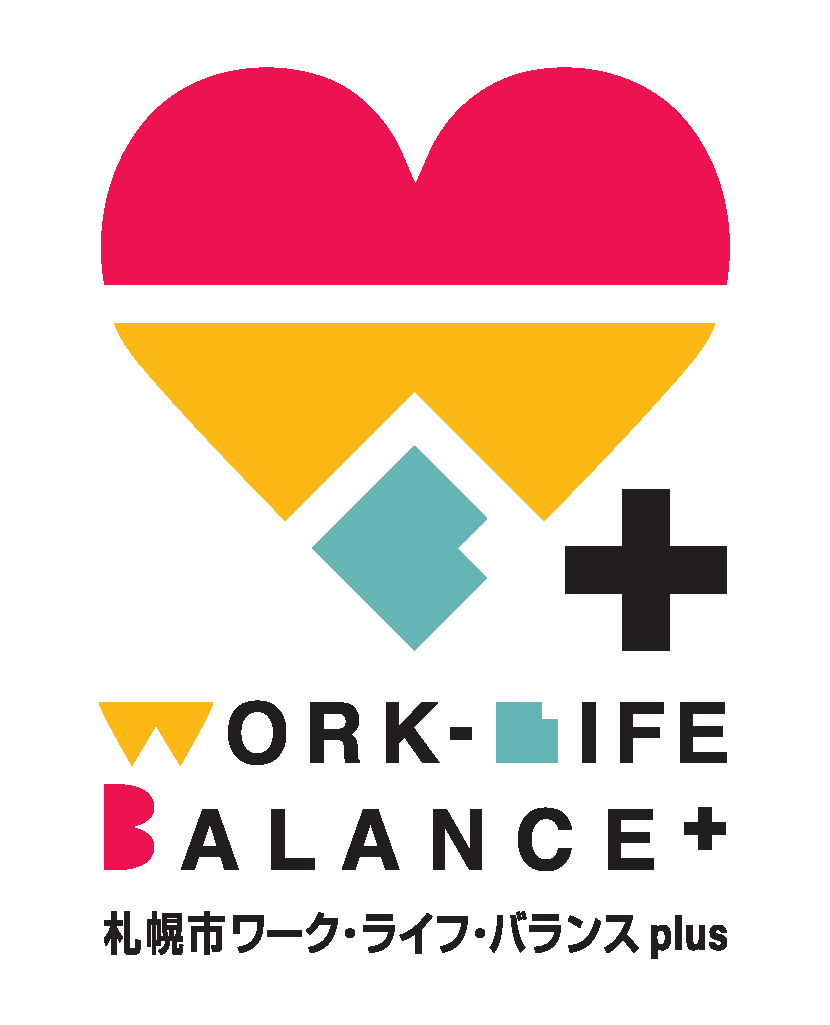地震や台風、水害といった自然災害が頻発する今、、、
突然やってくる「もしも」の時、私たちの暮らしを支えるエネルギーがどうなるか考えたことはありますか?
今回は、家庭でよく使われる3つのエネルギー:灯油・LPガス(プロパンガス)・都市ガスについて、災害時の「備え方」と「使いやすさ」を比較しながらご紹介します。
都市ガス

✅ 特徴
・ランニングコストが低く、利便性が高い
・都市インフラの一部で、管理が行き届いてる
・震度5強以上で自動遮断→供給停止される安全設計
・地震対策が年々進化している
⚠️ デメリット
・地下配管が損傷すると復旧間で数日~数週間かかる
・地震や津波、地盤の液状化などの影響を受けやすい
・避難所や一部地域に優先供給され、一般家庭への供給が後回しになるケースもある
・家庭では専門業者による復旧確認が必要
💡 備えのポイント
・カセットコンロとガスボンベを非常時に常備
・電気もガスも使えない事態に備えて、灯油・LPガスとの併用を検討
・安全装置付きのガス機器を選び、万が一の漏れにも備える
日常は便利、でも災害にはやや弱い
都市ガスは、地震などの災害発生時に自動でガスの供給を停止する仕組みがあり、火災やガス漏れを防ぐという点では非常に安全性の高いエネルギーです。
しかし一方で、配管の点検や安全確認、復旧作業には専門の技術が必要なため、再び使えるようになるまでには数日から数週間かかる場合もあり、災害時の即時利用には向いていません。
LPガス(プロパンガス)

✅ 特徴
・各家庭ごとにボンベで供給されているので、地域インフラに依存しない
・被害が少ない場合、数日以内に使えるようになるケースが多い
・配達・交換も柔軟で、災害時でも復旧が早い(ガス会社による個別対応)
・普段からLPガス契約がある家庭は非常時に強い
・防災用プロパンガス(LPガス)発電機を使えば、災害時でも電気の使用が可能に!
⚠️ デメリット
・ボンベの転倒や破損によるガス漏れリスク
・LPガスは「各家庭に配送される」エネルギーであるため、道路が寸断された場合や人手不足が生じた場合、供給が遅れることがある
・個別配送による、配送・運搬費用が上乗せされ価格は都市ガスよりやや高め
・使用機器はLPガス専用品が必要
💡 備えのポイント
・専用器具(ガスコンロや湯沸かし器)の停電対応可否を確認
・LPガスボンベの設置場所は安全・転倒防止対策を万全に
・防災向けプロパンガス発電機を備えておくと、万が一の時にも安心
自立型で災害に強い万能エネルギー
プロパンガスは、都市ガスとは違い、各家庭ごとに設置されたボンベからガスを供給するしくみになっています。
このため、災害で配管が破損する心配がなく、被害が小さければ比較的早く復旧できるという大きなメリットがあります。
実際に、地震後もプロパンだけはすぐに使えたという家庭も少なくありません。
一方で、ボンベが転倒すると危険があるため、しっかりと固定し、使用時には必ず換気と火気管理に注意することが大切です。
もしもの備えに!防災向けプロパンガス発電機がオススメ

HONDA×YAZAKI 防災向けLPガス発電機 詳しくはこちら
HONDA×YAZAKI 防災向けプロパンガス発電機は、災害に強くクリーンなエネルギーであるLPガスによる発電システム。
ご家庭にあるLPガスが発電用エネルギーとして利用可能に。最大約110時間*1運転時間で万一の長時間停電にも安心。
事務所や家庭用として即使用可能な低圧タイプで、本田と矢崎の共同開発モデルです。
簡単接続で、災害時・停電時にも電気が使えるので備えておくと安心です。
*1 定格で使用した場合、LPガス50kg容器満タンで約110時間使用可能。ただし、エンジンオイル等のメンテナンスが必要。
こんな人にオススメ
・災害・停電時の電源確保をしたい家庭
・ガスボンベがすでに家にある人(LPガス契約者)
・ガソリンを保管したくない人、安全を重視する人
灯油

✅ 特徴
・ポリタンクで備蓄可能(※保管には注意)、比較的入手しやすい
・電気を使わない反射式石油ストーブや芯式ストーブなら、停電でも使える
・特別な設備や契約が不要で、普段の生活で既に使っている灯油機器で対応できる可能性が高い
・ガソリンスタンドやホームセンターなど、調達手段が複数ある
・少量でもしっかり部屋が暖まる
⚠️ デメリット
・換気が必要。一酸化炭素中毒のリスク
・地震時は火災に注意。揺れが続く間の使用は控える
・灯油の長期保管は劣化するため、定期的な入れ替えが必要
💡 備えのポイント
・冬場に備えて、ポリタンク2個分(合計36~40L程度)の灯油を備蓄しておくと安心
・保管は風通しのよい冷暗所で行い、火気厳禁・密閉管理を徹底
・反射式ストーブなど電気不要の暖房器具を準備
家庭で備えやすい、暖房の強い味方
「昔ながらの灯油ストーブ」が今、防災の観点から見直されています。
灯油は、家庭で備蓄できる数少ない燃料の一つであり、電気やガスが止まった場合でも、電源不要の石油ストーブを使えば暖房や簡単な調理が可能です。
とくに寒冷地では、震災時に命を守る重要なエネルギー源となります。
ただし、使用中は必ず換気を行い、一酸化炭素中毒や火災に注意する必要があります。また、灯油は長期間保管すると劣化するため、定期的な入れ替えと安全な保管場所の確保も重要です。
まとめ
災害に強い暮らしは「分散型エネルギー備蓄」
♦灯油は停電時の暖房対策に有効で、家庭に手軽に備えられる
♦LPガスは完全自立型で、調理・給湯・暖房すべてに対応可能な最強のエネルギーではあるが、機器がLPガス専用でなければ使えない
♦都市ガスは平常時に最も使いやすく、安全装置や復旧体制も進化しているが、災害時は代替手段が必須
といったように、それぞれのエネルギーには災害時における弱みと強みがあります。
防災において最も大切なのは、一つのエネルギーに依存せず用途に応じて複数の手段を備えておくことです。
たとえば、「LPガスを主力にしつつ、灯油ストーブを備え、カセットコンロを補完的に活用する」
など、分散型のエネルギー備蓄体制を整えておくことが、非常時の安心と生存に繋がります。